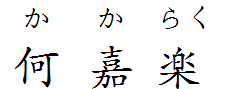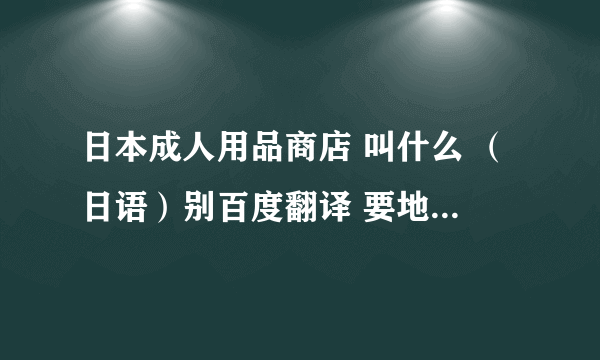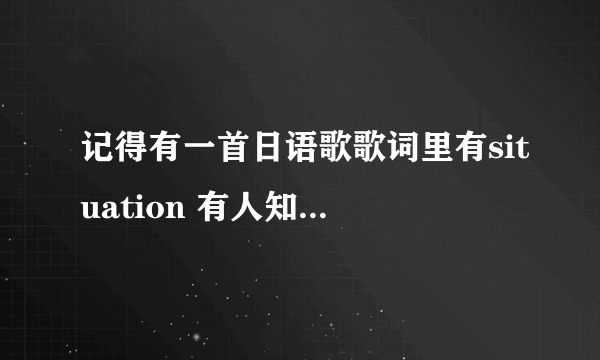求小森阳一先生的《ニホン语に出会う》日语原文。在这里先谢谢了。
的有关信息介绍如下: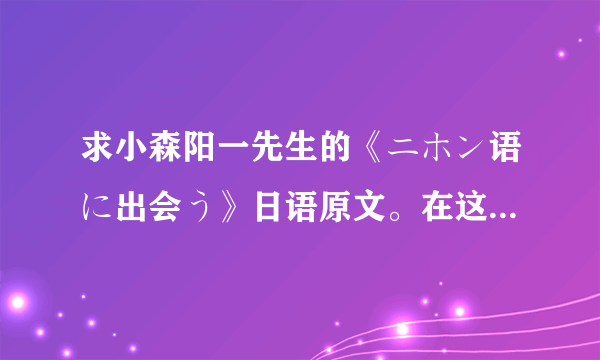
私が日本に帰国したのは、小学校六年生の年末だったので、学校へ行き始めたのは三学期がはじまっ型竖てからでした。最初の违和感は、一日目の帰りに感じました。下駄箱から靴を出していると、ジロジロとこちらを见るみんなの视线に気づきました。はじめは何のことだかよくわかりませんでしたが、みんなが上履きから履きかえている报は、すべて同じような、いわゆる「运动靴」であるにもかかわらず、私だけが、革靴を履いていたのです。宫沢贤治の『风の又三郎』に出てくる転校生の高田三郎が「赤い革の半靴そはいていた」ことで、「あいつは外国人だな」と言われてしまうのと、同じまなざしが、私を射すくめていたわけです。それから二周间ほどたつうちに、あることに私は気がつきました。教室で私が何かを言うたびに、まわりの子が笑いをおし杀しているような雰囲気になり、离れたところでは、あからさまなクスクス笑いが起きていたのです。私は、自分の使用する日本语に、それなりの自信をもっていました。プラハにいる间中、母亲は日本语を忘れさせてはならないと、小学校でやるべき全教科についてかなり热心に教育してくれましたし、私としても教科书に书いてあることは身につけていたつもりでした。また、ときおりやってくる日本からのお客様を迎えたときも、必ずといってもいいほど、私の使う日本语はきれいだとほめられたものでした。ですから、私としては自分が话す日本语に、何か欠陥があるなどとは思ってもみなかったのです。ある日、例のクスクス笑いにがまんならなくなった私は、立ち上がって、みんなにむかって、何がそんなにおかしいのか、という怒りをぶつけました。しかし、かえってきたのは教室全体をゆるがすような大笑い。それは、そのとき私の口をついて出たことばが、「ミナサン、ミナサンハ、イッタイ、ナニガオカシイノデショウカ」という、完全な文章语だったからです。つまり、私は、ずっと教科书にかかれているような、あるいはNHKのアナウンサーのような文章语としての日本语を话していたのであり、そのことを笑われていたわけです(このような话しことばを话す人とこれまでで一人だけ出会うことができました。大江健三郎さんのいくつかの小说に出てくるイーヨー=光さんです)その日から私は、周开の友达がどのような话し方をするのかに、注意深く耳を倾けるようになりました。そして、话しことばとしての日本语が、文章语としての日本语とはおよそ异质なことばであることに、毎日毎日気づかされていくことになります。现代の日本语は「口语体」で、话しことばと书さことばが一致した「言文一致体」である、という教科书に记されたウッに、そのとき身をもって気づかされることになったのです。たしかに、プラハにいるときも家の中で、父や母とは日本语で会话をして迅穗いましたが、考えてみれば、小学生の男の子が、亲とそれほどまとまった话をするわけでもなし、また教科书的な「正しい日本语」をしゃべっていたからといって、亲としてとがめる理由もなかったでしょうから、私の教科书的文章语としての话しことばは放置されていたわけです。友达の话しことばを観(聴)察するようになった顷、最も奇妙に思えたのは、日本语の话しことばは、决してそれ自体として完结するような、主语と述语がはっきりしたような言い切りの形をとらない、ということでした。言っていることの半分以上を相手にゆだねるような、微妙な暧味さの中でことばが交わされている、ということは一つの惊きでした。中学校へ入って日本语の使用をめぐるもう一つの困难に直面することになります。小学校のときのクラスの友人たちは、とりあえずチェコスロヴァキアという、ほとんビきいたことのない国、知っているとすれば体操のチャスラフスカ选手ぐらいという、よくわからないところからやってきたへんな転校生であるということを认知してくれていましたから、まあ少しぐらいおかしなこと卜昌大をしてb、あいつならしかたがないと思ってくれる寛容さを示してくれていました。けれども中学に入ると、そうはいきません。生徒たちはいくつかの小学校から来るわけで、しかも、同じ小学校でも别のクラスの子とはっきあっていませんでしたから、私の异常行动は、ことあるごとに摘発されることになります。なにしろ、外见は、肌の色も同じ、眼も细く、鼻も低い、まごうことなき日本人なわけですから、そういう奴が、理解しがたいことやみんなと违った行动をとることは、均一であることが好まれるこの国の学校社会では、ことさら目立ってしまったのです。日本の中学校での不幸の一つは、ロシア语学校に通い、とりわけ他の社会と比べて浓密なロシア人同士の身体的接触をめぐる生活习惯を内面化してしまっていたところにあります。ロシア人は、出会った人に亲しさを表明するために、男性同士でも、女性同士でも、そして男性と女性であっても、正面から肩を抱き合い、頬にキスしたり、頬を接触させたりします。小学校六年の三学期のときは、ものおじしてもいましたし、自分の话しことばの异様さをめぐって先制パンチを受けていますから、あまり身体的な生活惯习は出ていなかったようです。けれども、亲しくなった友人からは、事後的に、つまり中学での私の异常行为が问题视されたさいに、「オレもコモリに抱きつかれてキモチワルカッタよ」という告白をうけました。そう、私は、友だちを増やしたい一心で、少し言叶をかわすようになった男の子にも女の子にも、握手を求め、抱きつき、あまつさえキスをしようとしていたわけです。もちろん、数回にわたる、异なった相手からの强い拒绝反応によって、日本人は、そのようなとはしないのだということをいやというほど思い知らされましたが、时すでに遅しで、私のまわりには、「抱きつき魔」、「キス男」といった骂倒のことばが飞び交い、「スケベ」、「エッチ」という当时の私には意味のわからぬことばを投げかけられるようになってしまいました。日本における通常の人间関系では、身体的な接触は、ただちに性的な意味を持ってしまうこと、さらには性をいやらしいこと、下品なことと感じている人が多いということをつくづく思い知らされました。これはもう、自分の文化的身体をまるごと封印するしかありません。けれども、それだけでは済みませんでした。异文化としての自分の身体を封印した私は、それなりに操ることができるようになった日本语のことばに頼って友人をつくろうとしましたが、ここでも大きな过ちを犯したようです。私の通っていたロシア语学校のクラスには、ロシア人以外の子供が必ずいました。多くはかつての东欧圏の子どもたちでしたが、アフリカ圏やアジア圏の子どもたちもいました。それぞれの国の文化的事情の违いがかなりある时代でしたから(いまの世界的な文化の均质性こそ异常だと思いますが)、生活习惯のレヴェルでお互いに感じる违和感については、きちんと言语化して、お互いに纳得しておかないと友达にはなれません。つまり、おまえのこういうところは好きだからおまえと友达になりたいが、おまえのこういうところはいやだ、というふうに、相手の好きなところときらいなところを明确にしたうえで友达づきあいを始めていくわけです。同じことを日本の中学で、とくに女の子に対しやってしまったことを想像してみてください。一学期の终わる最後のホームルームは「亲も言わないようなひどいことを言うコモリクン」についての话し合い(纠弾集会)になりました。友达になることができなかったばかりでなく、平気で面と向かって人の悪口を言う思いやりのない奴だ、ということになってしまったのです。中学一年生の夏休みが始まる顷には、自分は日本の文化と社会的生活惯习から、完全に浮き上がっていることを自覚しました。その夏休みに、私は読书感想文を书くために、夏目漱石の『吾辈は猫である』を読みました。抱腹绝倒のユーモア小说というふれこみだったので、少しは暗い気分が晴れるかと思っての选択でした。しかし、逆効果で、読みはじめた瞬间から涙が止まらなくなりました。なぜなら、「このネコはボクだ!」と思わざるをえなかったからです。生まれた直後に、人间という异种によって亲や兄弟から引き离され、たった一匹で苦沙弥先生のところに迷い込み、人间のことばはわかるが、こちらからは人间に何も伝えることができず、一度も食べたことのなかったモチを喉につまらせ生き死にの境でもがいているのに、人间たちは「ネコジャ踊り」だと大笑いする、谁一人として自分のことをわかってくれない、そんな物语に読めてしまったのです。その意味で、「吾辈」が人间世界に対して彻底して批判的になるのもよくわかりました。あいつらが、常识だと思い込んで、あたりまえのこととしてやっているふるまいは、相当におかしなことなんだ、と诉えてくる「吾辈」に、十三歳の私はいちいち同意することができました。人间世界に対する「吾辈」の违和感は、そのまま日本人が自明化している文化的・社会的な暗黙の了解事项に対する私の违和感と重なっていきました。でもそれは决して笑えるような类の同意ではなく、悲惨な状况を愚痴る情なさにおける共感だったのです。もちろん、そのような思いを缀った読书感想文が、どのような末路をたどったかはおわかりでしょう。以来、私は「国语」という教科をうようになります。